最新のカルシウム・カルシウムサプリメント比較ランキングを、口コミ&評判つきでご案内します。

トップページ > コラム/カルシウムの基本「他の疾患との鑑別診断」
当サイトの目的は、老人性骨粗鬆症の成因、診断方法、予防など治療につきできるだけわかりやすく最新の知識を解説し、本症に対する理解を深めていただくとともに、骨粗鬆症対策として有効なカルシウムの働きや効果・効能、副作用についても知っていただきたいということです。読者の皆さんの健康で快適な生活の一助となれば幸いです。
目次
- トップページ
- 2019年8月のカルシウムサプリメントランキングはこちら
- カルシウムの基本
-
- カルシウムの基本「カルシウムの機能」
- カルシウムの基本「血中カルシウムの調節機構」
- カルシウムの基本「カルシウム欠乏」
- カルシウムの基本「カルシウムと高血圧」
- カルシウムの基本「老化と骨」
- カルシウムの基本「骨粗鬆症とは」
- カルシウムの基本「骨粗鬆症は50歳台閉経後の女性に多い」
- カルシウムの基本「骨の代謝」
- カルシウムの基本「骨吸収と骨形成の調節に関与する因子」
- カルシウムの基本「骨粗鬆症がなぜ起こる?」
- カルシウムの基本「なぜ骨代謝異常がおこるのか」
- カルシウムの基本「骨粗鬆症とホルモン」
- カルシウムの基本「骨粗鬆症に対するカルシトニンの効果」
- カルシウムの基本「骨粗鬆症とカルシウム」
- カルシウムの基本「骨粗鬆症と行動因子」
- カルシウムの基本「骨粗鬆症と病気」
- カルシウムの基本「レントゲン写真による骨粗鬆症の診断」
- カルシウムの基本「他の疾患との鑑別診断」
- カルシウムの基本「骨粗鬆症の予防」
- カルシウムの基本「骨粗鬆症の治療」
- カルシウムの基本「大切なカルシウム摂取」
- カルシウムの基本「女性ホルモン」
- カルシウムの基本「様々な作用をもつカルシトニン(1)」
- カルシウムの基本「様々な作用をもつカルシトニン(2)」
おすすめサイト
- ヒアルロン酸比較ランキング
- サプリメント比較ランキング
- 青汁比較ランキング
- 黒酢にんにく比較ランキング
- 乳酸菌・ビフィズス菌/クチコミ比較ランキング
- ファンデーション比較ランキング
- ヒアルロン酸サプリメント比較ランキング
- コンドロイチンサプリメント比較ランキング
- 白髪染めヘアカラートリートメント比較ランキング
- DHA+EPAサプリメント比較ランキング
- 青汁比較
- コラーゲン比較ランキング
- 認知症ネズミが教えてくれた、記憶の老化対策サプリ比較ランキング
- 関節痛サプリメント比較ランキング
- プラセンタ比較ランキング
- 美肌サプリ比較ランキング
- 黒酢比較・香醋比較ランキング
- ブルーベリー比較ランキング
- グルコサミンサプリメント比較ランキング
- 美容液比較ランキング
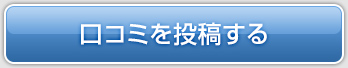
骨量の減少をきたす疾患は他にもたくさんありますので、これらの疾患を鑑別しなければなりません。
鑑別診断に必要な検査として実施すべきものに血清のカルシウム、リン、アルカリフォスファターゼ(Al-P)の測定があげられます。
尿中のカルシウムの測定、BMA、DPA、CTなどによる骨量の測定も必要です。
なぜこのような血清成分の測定が必要かといいますと、レントゲン写真のみでは骨粗鬆症とまぎらわしい他の疾患との鑑別が困難だからです。
まず鑑別すべきものの第一番目にosteomalacia(骨軟化症)があり、それから原発性副甲状腺機能充進症、腎性骨異栄養症、多発性骨髄腫、癌の骨転移といった他の疾患があります。
骨粗鬆症では血清カルシウム、Al-Pは特別な場合をのぞいて正常です。
骨軟化症では血清カルシウムがやや低下し、リンが下ります。Al-Pは高いという生化学上の特徴があります。
原発性副甲状腺機能亢進症では血清のカルシウムが高くリンが低いという特徴があります。
腎臓が悪いときには血清リンが上がり、BUNが高くなってきます。それから老人で非常にまぎらわしいのは多発性骨髄腫で、この場合にはM蛋白が認められます。
癌の転移の場合は全身の状態が鑑別上の参考になります。
一般に癌の骨転移があるのは末期の状態に多いものですから、骨以外に癌があるかどうかということを見出すことが決め手になります。
こういう疾患を除外したあとに残るのが骨粗鬆症ということになります。
骨粗鬆症でも原因疾患の明らかな場合があり、それはsecondary osteoporosisと呼ばれています。
原因疾患としては甲状腺機能充進症、Cushing症候群、ステロイド投与、その他の疾患があります。
しかしこういうものは非常に少なく、90%はprimary osteoporosisと呼ばれるものです。
したがって骨粗鬆症の診断というのは、現在では除外診断の上に成り立っているのです。
secondary osteoporosisを除いて残るものがprimary osteoporosisとするという手続きで診断を行うわけです。
(続く)
カルシウムの健康効果にご興味がある方は、カルシウムサプリメントを試してみてはいかがでしょうか。
>>>最新のカルシウムサプリメント比較ランキングはこちら